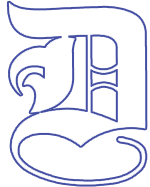
過去の企画展
― Exhibition ―
獨協学園の学租・大村仁太郎について
第四代校長大村仁太郎のころ、獨逸学協会学校は大きく変わろうとしていた。創立当初の準官立的な高等教育機関としての性格は、いくつもの官費助成が打ち切られたうえ、法曹司法官僚養成のための専修科が廃止されたことによって失われていった。学校の財政は悪化し、獨協はいやおうなく普通教育の中学(獨逸学協会学校中学)へと縮小退却しなければならなかった。けれども見方を変えれば、こうした事態に遭遇するなかで、獨協は自立した私立学校へ脱皮したとも言えるのである。
創立時の明治元勲たちの多くは経営から手をひき、学校の現場では新しい世代の教育家・研究者・教師たちが、独自の教育を展開し始めていた。そこではドイツ語中心の文化性に富んだ教育がなされ、多くの生徒を医学部系の大学へ進学させるだけでなく、人間の本質的なところで、ゆたかな人格を育てていた。こうした転換期の獨逸学協会学校中学を支えた中心的人物こそ大村仁太郎であった。
大村仁太郎は獨協教育の系譜の中では、学祖と言うべき人物である。卓越したドイツ語学者であった彼は、まず外国語を習得することが人の視野を広げ、また泰西(たいせい)(ヨーロッパ)の文物制度にたいする、観察および思考の力を養うとみていた。この見識は獨協の教育にいかされ、生徒たちの精神を大きくひろげ、狭さや偏りのない近代的な知性を育んだ。
詩人・劇作家である木下杢太郎(きのした・もくたろう、本名太田正雄、明治36年卒、東京帝国大学教授、ハンセン病の先駆的研究者で患者の人権を強く訴える)のような、難病弱者にどこまでも寄り添うた医学者を獨協が輩出したのは、大村時代の教育における近代的知性と無関係ではない。
大村は20世紀初頭のドイツに滞在して、あたらしい教育思想(ザルツマン、マティアスなど)を学んだ。そして家庭・婦人・子どもに目を向け、教育での人格の形成をこころざした。かれは「(わが国の)教師はひたすら知識の注入にばかり努めて、人格の養成などは他事(よそごと)のように思って居る」と学校教育を批判する。また「子供はあまり怖がらせると嘘を吐くようになる」といい、さらに「人が打擲(ちょうちゃく)に慣れると、身体の神聖などと云う考えがなくなって、自然から恐るべき結果を来たす」とも述べる。儒教的教育観が支配的だった当時ではめずらしく、子どもの目線に立って教育を考え、人格と密接に結びついている「身体の尊厳」に注意をはらった。
ドイツ留学を終えて帰国した大村は、学習院兼任から獨協専任へ転じ、校長として生徒教育と学校経営に全力をあげた。普通中学へ学校が後退したころ、かれは生徒を励ますためドイツ文字(華文字)でD(DokkyoのD)をあしらった校旗をつくり、さらに校歌を制定した。ドイツ語学と結合した、かれの人格主義的な知的センスは、この頃にもっとも輝いたといってよい。その後わずか45歳で人生を閉じたが、かれの教育精神が明治期の獨協に残したものはまことに大きかった。それは大村時代の獨協が、知的退廃の最たるファシズムの時代に、「理性」と「道理」を掲げて屈しなかった天野貞祐を生み出した、という一点からだけでも明らかである。
このたびの企画展でわたしたちは、以上のようなドイツ語学者であり近代教育家でもあり、そして獨協の教師・校長でもあった大村仁太郎のすがたを紹介し、かれが抱いた教育精神をできるだけ具体的に照らし出したいと考えている。
